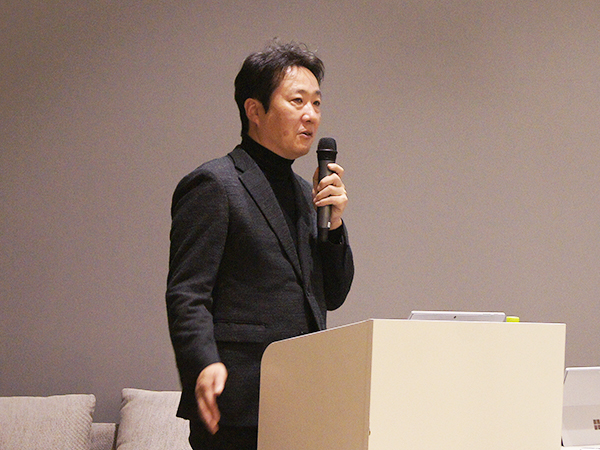【講演1】
「常石グループが見据える環境ビジネス」
常石商事株式会社 代表取締役副社長 津幡靖久氏
福山市で海運業と造船業を軸に、エネルギー、環境、ライフ&リゾートなど多角的に事業を手掛ける常石グループ。グループの中で商社機能およびエネルギー関連事業を展開している常石商事は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境負荷低減と事業規模拡大の両立を目指しています。
「当社の収益基盤は鉄(船の鋼材やパイプ)と石油(ガソリンや船舶用の重油)の二つです。いずれもCO2排出量の多い事業であり、今後飛躍的に成長することは見込めません。石油にいたっては将来的にゼロになる可能性もあります」と津幡氏は危機感を募らせます。
今後、国内で半導体やデータセンターなどへの大規模投資による電力需要の増加が見込まれることから、同社は太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業に重点を置き、自家消費型太陽光システムの販売、余剰電力の自己託送やコーポレートPPA(電力購入契約)による電力供給事業に注力しています。また、地域で電力が不足している場所へ余剰電力を振り分ける仕組みを構築中です。同社の休業日に発生した電力をグループ会社の遊園地に供給するプロジェクトは、県の太陽光発電施設導入事業補助金にも採択されました。さらに、大型蓄電所の設置も視野に入れており、採算性などの課題をクリアした上で、2030年頃の実現を目指すとしています。
また、新たな再生可能エネルギーとして潮流発電にも着目しています。地元の瀬戸内海は世界有数の急流海域でありつつ波が穏やかなため、太陽光発電と比べても発電時間が長く、安定的な供給が期待できます。今年、潮流調査やシミュレーションを実施したところ、手間やコストなどの課題が多いことが判明しました。このため、同社はオープンイノベーションに乗り出し、株式会社ハイドロヴィーナスとタッグを組み、課題解決に向けて取り組みを進めています。「課題は山積していますが、最終的には島や港湾の電力を潮流発電で賄えればと考えています。地域特性を生かし、瀬戸内をクリーンエネルギーの先進地域にしたいですね。これにより雇用も生まれ、地域の活性化にも貢献できると思います」(津幡氏)
「環境ビジネスをどのようなチャンスと捉えているか」という会場からの質問に対し、津幡氏は「日本が蓄電池の分野で遅れを取っていることをふまえると、ものづくりについてはスピード感が重要です。ただし、私たちのように技術を導入する立場では、先取りしすぎても慎重になりすぎても良くありません。補助金も含め、行政の後押しを期待しています」と答えました。また、「再生可能エネルギー事業で、どのような企業と協業を望みますか」という質問に対しては、「たとえば太陽光発電では設備の施工のほか、潮流発電や蓄電池においても優れた技術を持つパートナーを幅広く求めています。私たちが持つ顧客との接点を生かして技術やノウハウを発揮したい企業様には、ぜひ当社にお声がけいただきたい」と、呼びかけました。